lacrimosa
∞ lacrimosa
この地方では、めったに雪は降らない。
故郷の街に帰ってきたのは、そんな特別な日だった。
うっすらと薄化粧して青年を出迎えた白い街は、薄闇に浮かび上がって見えた。
「ついてねぇ……」
この寒さを凌ぐには心もとない薄手のコートの襟を寄せて、ラヴァンは苦々しく呟いた。そんな心中を体現するように、大きな白い息が吐き出される。
背中には、気を抜けば後ろにひっくり返って亀よろしく起きられなくなりそうな大荷物。この格好で街中央まで雪道を歩くなんて、神経がすり減りそうだ。
もう一度だけ大きく溜息を吐いてから、青年は意を決して歩き出した。
昼ごろに到着するはずが、乗りあった馬車の車輪が急な降雪で思うように進まず、日暮れになってしまった。
もうすぐ夜が来る。肩を縮こまらせながら足早に帰途につく人々の間を抜け、ラヴァンはしんしんと降る白い光の祝福を浴びながら進む。
城下町を抜け、貴族街に踏み入れると、雪の夜に染み入るような美しい歌声が聞こえてきた。その美声に導かれるように、青年はある屋敷の扉の前に立った。
かじかむ手で扉をノック。ほどなくして扉を開けて出迎えてくれた給仕の女性は、目を丸くした。
「あらお坊ちゃま!? おかえりなさいませ!お帰りのご予定でしたか?」
「あー、やっぱり……久しぶりティエリ。とりあえず、荷物を片付けるの手伝ってほしい……はー、疲れた……」
広い玄関に入って真っ先に荷物を下ろし、ラヴァンは体に積もった雪を払った。ああ、体が軽い。
「いつこちらに?こんな大荷物、ご連絡いただければセントラクスまで受け取りに向かいましたのに……」
荷物を端に寄せて給仕が不思議そうに言うと、また玄関の扉がノックされた。
扉を開いた給仕が何かを受け取り、ドアを締めて振り返る。彼女の手には、ラヴァンの予想通り、一通の手紙があった。
「あら?このお手紙……お坊ちゃまが差出人ですわね」
「僕のほうが早かったな」
見覚えのあるそれを一瞥し、ラヴァンは苦笑した。
出立前に、家に帰ることになった旨を書いた手紙を出したのだが、間際に出したので間に合わない予感はしていた。大方、自分が乗ってきた馬車に一緒に載せられていたのだろう。
「早く帰ってきたかったから、自分で荷物をまとめて出てきたんだ」
「ふふ、今日は大事な日ですものね。お荷物は手分けしてお部屋に運んでおきますわ。ご夕食はこれからですからお待ち下さいね」
「ああ、ありがとう。荷物は僕も運ぶよ」
伸びをしてラヴァンが申し出ると、給仕の女性は上品に口元を手で隠してくすりと笑った。
「そんなお疲れのお顔で言われましても説得力がありませんわ?それより、早くお嬢様に会ってあげてくださいませ」
「……そんなひどい顔してるか?」
「ええ、ご友人に大事なご本をとられて泣きじゃくっていた時のようですわ」
「そ、それは昔の話だろ!? しかもそんなに泣いてない!」
「ふふふ、ではまた後ほど」
青年が子供の頃から屋敷に仕えている彼女には、敵う気がしない。
ラヴァンは女性に荷物とコートを預け、一人、歌声が響く方へ向かった。すれ違う給仕たちに簡単な挨拶をしながら歩き、彼はひとつの部屋のドアをノックした。
歌声が止んだ。
「ミオネ、入っていいか?」
「え……!? 兄上ですかっ!?」
甲高い少女の声とともに、扉が勢い良く開け放たれた。
桃色に近い、淡い紫の髪が空気になびいて揺れる。驚きにまんまるになったライトシアンの眼が、ラヴァンを見つめていた。
少女の顔が嬉しそうに綻ぶのには、そう時間はかからなかった。
「本当に兄上だ!お久しぶりです♪ あは、ひどい顔の兄上も素敵ですね☆」
「そりゃ、街の入口からここまで、最悪のコンディションの道中を2年分の荷物背負って歩いたらこうもなるだろ……?」
「あはは、ゲブラー所属の方の言うセリフとは思えない貧弱ぶりですね♪」
調子よくころころ笑う少女は、ラヴァンより小さい。小柄な体躯には、純白のドレスをまとっていた。それが特別な日に着る衣装であることは、服飾に疎いラヴァンでも知っている。
「いつ来ても歌の練習してるな、お前は」
「えへへ、聖歌隊のルーキーは忙しいのです☆ まだまだ練習が足りないですから!」
「そっか、頑張れよ。……で、ミオネ。お前、今日で13歳だろ?ほら」
ラヴァンは、おもむろに懐から何かを取り出した。ミオネが首を傾げながら両手を差し出すと、そこにそっと置かれたのは、大きな桃色の造花があしらわれた髪飾りだった。
「えっ?あ……それで兄上、今日にあわせて急いで帰ってきてくれたんですか?」
「大幅に予定が狂ったけどな……セントラクスで買えればよかったんだが、時間がなくてさ。馬車の中に行商人がいたから、そこで買った」
少女が早速頭につけてみると、髪色と相まって、髪飾りは馴染んでそこに収まった。
部屋のドレッサーで見目を確認して、ミオネはとても嬉しそうに兄を振り返った。
「さすが兄上、センスありますね☆ この髪飾り、気に入りました!」
「そりゃよかった」
女の子の趣味までは理解できているとは言い難いラヴァンは、妹の笑顔を見てほっと息をついた。
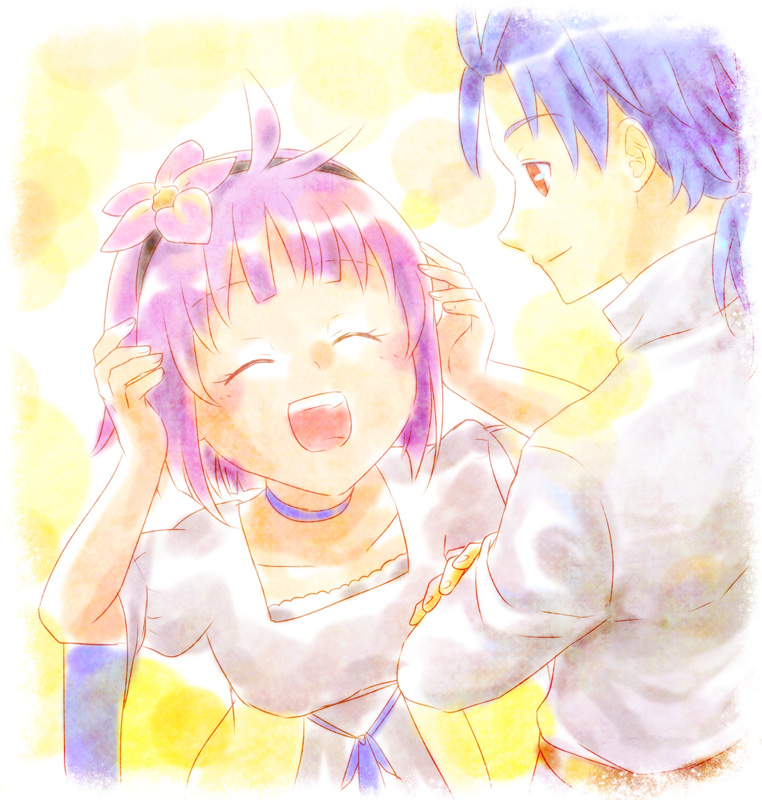
「ところで兄上、今年は連絡もないし、帰省はしないと思ってたですよ??」
「帰省じゃなくて引っ越す予定だったからな。片付けに手こずってたら連絡が遅れたんだよ。僕はここの配属になったから」
「あれ?でも、兄上はミディア配属って書いてましたよ?聖堂に人事一覧が届いてたです」
「その後に変えてもらったんだ。あとで訂正されたものが届くと思う」
セフィスの親衛隊という意味合いで言い渡される、ミディア配属。最高クラスの名誉を蹴って、2つランク下のここイクスキュリア配属を選ぶなんて、普通の人が聞いたら目を剥きそうだ。
「ミディア配属にはルナを推しておいた。……ミディアにはサリカがいるし、ルナが傍にいた方がいいだろ」
ラヴァンは、同期であり親友である男女の名前を挙げた。
初めて会った時から、時折サリカが遠くを見つめていることに気付いていた。心ここにあらずといった具合で、ひどく重症そうに見えた。彼が背負うものが何なのか、ラヴァンは今でも知らない。
誰かが傍にいないとふらっと消えてしまいそうな不安定さを、ラヴァンは信頼のおけるルナに預けた。
自分は、このイクスキュリアでやるべきことがある。
だからこそ、2年前、この家を飛び出したのだから。
「兄上が帰ってきたということは、これから毎日サリカ様のお話が聞けるんですね♪」
うっとりとした様子で、ミオネは両手を頬に当てた。心底嬉しそうな妹に、ラヴァンは少しだけ罪悪感に見舞われるのだった。
家にいない間も、妹とは文通をしていた。そこに綴るとりとめのない話の中に、サリカとルナの名前はよく挙げていたので、ミオネも二人のことはおおよそ知っている。
軽率に二人の話をしすぎたと、今では少し後悔している。
例えばこんなことを言ってくる。
「兄上、ルナ様にはちゃんと言ったです??」
「な、何を? ……いや、急に推して悪かったっていうのは言った方がよかったかも……」
「あは、兄上ったら絵に描いたような奥手ですね☆ ではでは、ルナ様宛にお手紙を書きましょ?きっと今からでも遅くないですよ♪」
「う、うるせーほっといてくれよ!出さなくていいって!」
キラキラと目を輝かせてドレッサーの引き出しからレターセットを取り出し始める妹を、ラヴァンは全力で止めた。
しぶしぶ便箋たちをしまったミオネに、ラヴァンはやっと本題を切り出した。
「ミオネ、ははう……お袋は、どうしてる?」
「母上はお変わりないですよ。今夜はミオネの誕生日なので、屋敷にいるはずです。兄上、夕食はまだですよね?一緒に食べましょ?」
「あぁ。なら……都合がいいかな」
「———何の都合がいいの?」
突然、二人以外の声が割り込んできた。
猛然と兄妹が廊下を振り返ると、一人の女性が佇んでいた。
真っ先に目についたのは、金の刺繍が施された真っ黒なマント。腰まで伸びた長い青髪は、肩口でゆるくまとめられている。
ラヴァンと同じ赤の双眸が、厳しい色を帯びて彼に向けられていた。
「……貴方に宣言する場を設ける手間がなくて、ってことだよ」
彼女が現れただけで、空気が清く正しく、まっさらになった。あまりに潔白すぎて息苦しいほどに。
普通の者ならこの魔力に絡め取られて、すぐさまこうべを垂れているだろう。神のように崇められる厳正なカリスマが、ひしひしと肌を叩く。
意識して立たねば膝を折ってしまいそうな相手に、青年は告げた。
「お袋。その座、僕が奪いとってやる」
——その夜、雪は涙のように降り続いていた。