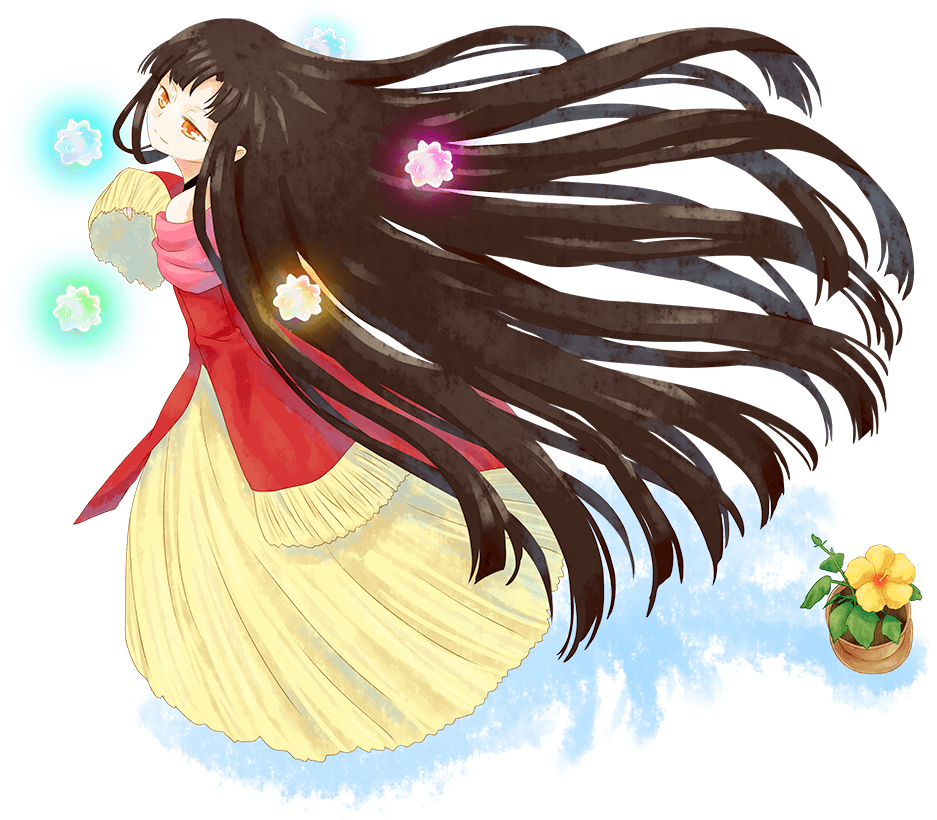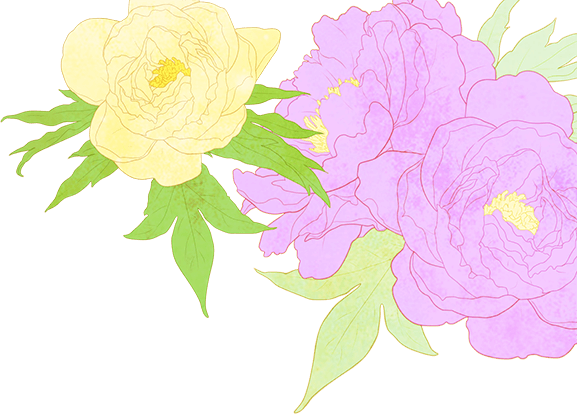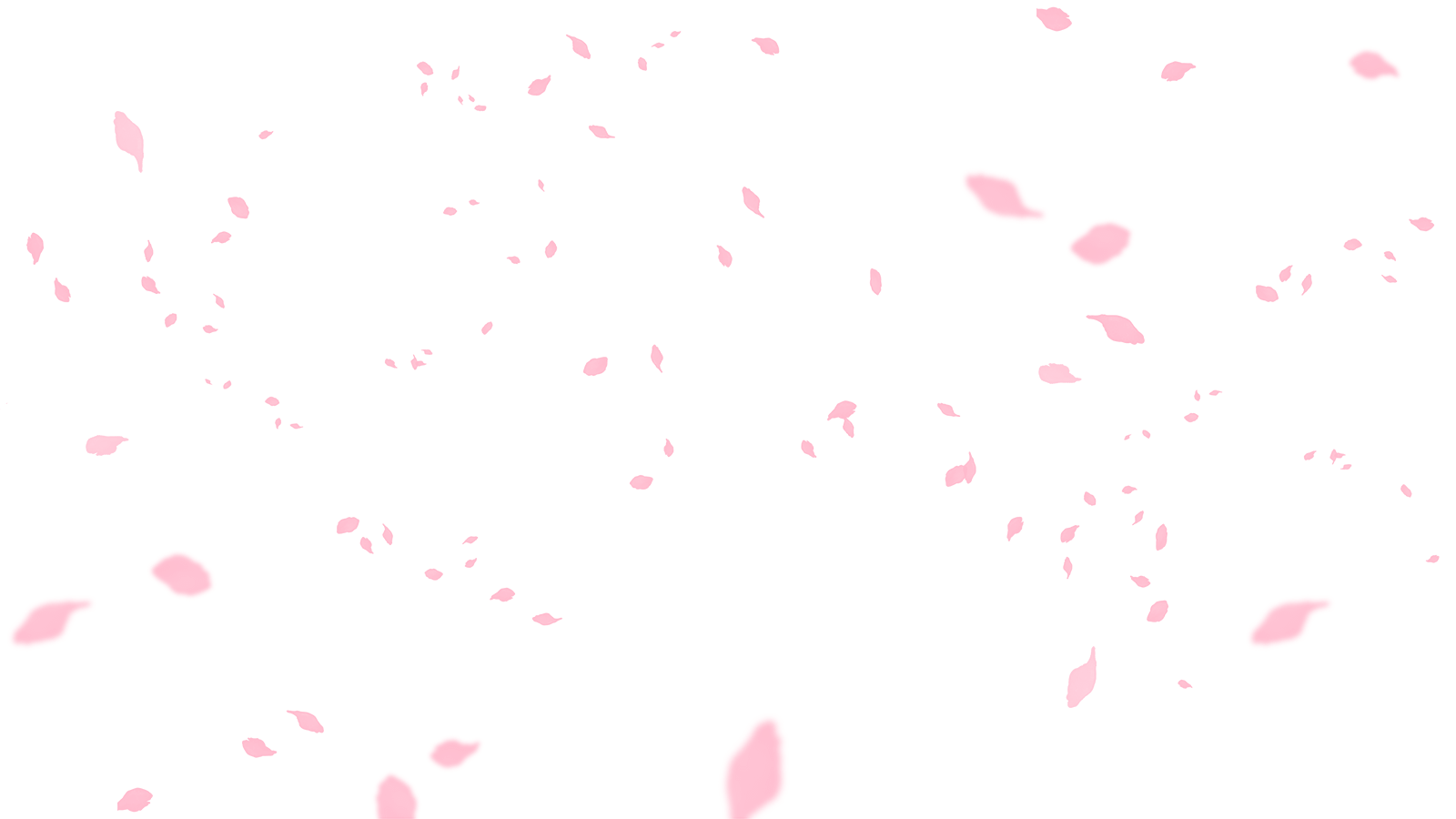1
9
夏は、嫌いだ。理由は単に、暑いからだ。
だから、日に日に寒くなってくるこの時期はほっとする。
ようやく、暑い季節が去るのだ。
2階の窓の外に見えるのは、中庭の大きな銀杏の木。
漫然と生活していると、秋なんて来たのか来てないのかわからないが、この席にいるとよくわかる。少し前に銀杏の葉は鮮やかに黄色に紅葉し、ここ数日ではらはらと落ち始めている。
「じゃあ1番を……沖澤」
視線を黒板に戻すと、教卓の前に立つ黒スーツの教師が、手元の名簿を見て言った。彼の背後の黒板には、数式が書かれている。
最後列の席の沖澤一夜が、あからさまに「マジかよ」という顔で、重そうな腰を上げる。
俺の名簿の前の沖澤が当たったということは、恐らく……、
「2番を加賀谷颯馬、3番を加賀屋悠。出て書いて」
やっぱり俺もなんだな……教師は名簿順で当ててくるから推測しやすい。ちなみに俺がフルネームで呼ばれる理由は、漢字は違えど「かがや」が二人いるからだ。
教師は黒板をコンコン叩いて示してから、沖澤の邪魔にならないように教壇から下りる。仕方なく俺も席を立って、すでにノートで解き終わっていた答えを一瞥してから黒板の前へと向かい、沖澤の後ろを通って左隣に立った。俺の右には、悠がすでに立っている。
沖澤が小声でヘルプしてきた。
「……颯馬、これどうやんの?因数分解できねぇよ」
「解の公式使うんだよ」
「あっ、そういうことか!うわー、マジかよ。めんどくせぇー……」
溜息混じりに言うと、面倒臭そうだった沖澤は、さらに面倒臭そうに大きな溜息を吐いた。
俺が途中の式を書いていると、今度は右隣の悠が、式を書いている途中で確認をとってきた。
「颯馬、3番って4だよな?」
「俺はそうなったけど」
「なら大丈夫だな」
仲間がいると知って安心したのか、悠の式を書く手つきがスムーズになった。
二人より早く書き終わった俺は、チョークを置いて自分の席に戻る。間違ってないかノートを確認して、閉じた。もうあと1分くらいで終わりだから。
沖澤と悠が、自分の机に戻る。沖澤は……残念ながら計算ミスをしていた。しかも超初歩的な。悠は完璧だ。
俺達が書き終わった答えを見て、教師は教壇の上に登り、時計を見上げてから黄チョークを手に取った。
「1箇所訂正して終わるぞー。沖澤、4×2は6か〜?」
「あ!!」
どっとクラスに笑いが巻き起こった。さっきまで真面目にノートをとっていて静かだった空気が、急に和やかになる。沖澤は自分の失態に苦笑した。
チャイムが鳴り、教師が教室から去る。4時限目だったから次は昼食だ。クラスの全員が、学食か弁当かの違いでバッグからそれぞれお目当ての物を取り出す。
俺も自分のエナメルバッグから黒いサイフを取り出していると、傍に誰かが立った。
「何食うかな〜………あ、牛丼とかいいなぁ。颯馬は?」
沖澤だった。俺と沖澤は、基本的に学食で昼を済ます。今日も例外じゃない。ちなみに食欲旺盛な沖澤は、毎日こうして昼飯で悩んでいる。
俺は……何にしようかな。
「……そばかな」
なんとなくさっぱりしたものを食べたいと思って、俺が席から立ちながら言った。
「じゃあ、対抗してうどんだ!」
「テキトウだな、いつもいつも……」
沖澤だからな……と、根拠がないようで、でも物凄く説得力のある言葉を内心で付け足して、俺は、いきなりハイテンションになった沖澤の後を追った。
* ※ *
11月中旬。秋だか冬だか、曖昧な境の頃だ。
俺……加賀谷颯馬は、高校3年生だ。俺の高校は進学校で、当然俺も進学だから、大学受験に向けて勉強中だ。成績は……多分、割といい方だと思う。学校内での話だけど。
ただ、俺はまだどの大学へ行くか、絞っていない。とりあえず、今の仮の目標は、沖澤と同じ大学だけど……特にその大学にやりたいことがあるわけじゃない。最終決定は、センター試験を受けた後になるだろうけど、そこで行きたい大学、やりたいことが本当に見えているか、自分でも漠然と不安だった。
流されるように進学するのは、なんとなく嫌だった。やるなら、やりたいことにまっすぐ向かいたい。贅沢かもしれないけど。
3年生だから、半年前くらいに部活は引退している。ちなみに陸上部で、中距離をやってた。大分、筋肉落ちたけど……。
だから当然、下校時間も早い。沖澤に街でブラブラしようとか誘われたけど断った。今日は本当に眠くてやばい。家帰ったら即行ベッドへゴーだ。
俺の家はどっちかっていうと田舎にあって、そこから街近くの高校に電車で通っている。徒歩で駅へ行き、15分くらい電車に揺られて降車する。
電車から降り、まばらな人込みに混ざりながら改札を抜け、地元の駅を出た。駅から自宅までも徒歩だ。駅前に立っている時計は、午後5時を差していた。
「はーっ」
なんとなく息を吐いてみると、息は白いモヤになって消える。太陽が沈むのが早くなってきていて、夏ならまだ昼間みたいに明るい時間帯だけど、空は真っ黒だった。
首に紺のマフラーを巻いているのに、首の後ろが寒くて、ちょっとマフラーの位置を調整する。それが済むと、ふと耳が寂しいことに気付いて、バッグからイヤホンを出して耳とスマホにつなぎ、少しかじかむ指先で操作して音楽を流す。そうしてから、ようやく歩き出した。
通い慣れた道は、ちゃんと前を見ていなくても大体歩けるものだ。携帯電話をいじりながら国道沿いの歩道を歩いて、少し反れた道に曲がり、ずっと歩いていくと、閑静な住宅街に入る。ここが俺の家があるところだ。
この住宅街、意外と広い。俺の家は、住宅街の奥の奥って感じのところにあって、ここからもまだ少し歩く。父さんも、何であんなところに家を建てたんだか……。
やることがなくなって携帯電話をしまった。すると今度は、なんとなく静寂が恋しくなった。……我ながら忙しい奴だ。俺は音楽と同じくらい、静寂も好きだったりする。イヤホンを外し、携帯電話とイヤホンを一緒に制服のポケットに入れて。
—————シャラン、
「………………?」
鈴のような音が、聞こえた気がした。
神社でよく見る、大ぶりの鈴がたくさんついた棒を振った感じの音だった。
そして、耳が痛くなるような静寂。
何事かと思って足を止めて顔を上げ………そして足を止めた。
………………夢、か?
家の灯りだけが闇に映える、人影のない道。俺の家は、この道をまっすぐ行って、突き当たりを右に折れたところにある。だから、当然まっすぐ進まなきゃならないわけだけど。
すぐ目の前。2歩くらい先が、淡く白く光っていた。
光っているのは、リンゴ程度の大きさの、コンペイトウみたいな虹色の固体。それが2つあって、その周囲を時計回りに回っていた。
「残り2つ、か……もうそろそろ、終が来るのう」
コンペイトウとはまた違う、目の前の虹色の光を見下ろし、そいつはそう言って、ほぅ、と小さく嘆息した。普通なら白くなる息だが……なぜかならない。虹色の光は、ふわりと空に溶けて消えていく。
夢でも幻でも見間違えでもなければ……そいつは、自らも淡く光を放っていた。恐らく10歳前後の少女。膝にも届きそうなくらい長い、切り揃えられた黒髪。身長は……多分、俺の腹より少し上くらい。ちなみに俺は、179cmと割と高いほう。
赤が基調の、なんとなく中華風な雰囲気の衣装。目は、実際には絶対有り得ないと思うオレンジ色だった。しかし不思議なことに、まるでそれらがすべて一体であるように、しっくりと調和していて違和感がない。
見た目だけならよくできたコスプレくらいに見えたが、その落ち着いたら佇まいだけが異質だった。
子供は、ようやく俺に目を向けた。子供特有の無邪気さとかそういうものがまったく感じられない理知の瞳が、俺を見定める。
「……まぁ、良いか。それもまた一興。そこの貴様」
子供らしい高音が、何処か年寄り臭い口調で言う。子供は、裾から手が出ない仕様らしい服で俺を差した。
「一人のつまらん鬼ごっこには飽きたのでな。貴様、終が来るまで私の相手をせい」
「……は?? いや……忙しいからまた今度」
大分落ち着いてきた俺は、要するに「遊んでくれ」と言っている子供に対し、多分言い訳ランキングトップだと思われる超ベタな返しをした。
すると子供は、途端にふてくされた顔になり、腕を組んでつまらなさそうに息を吐く。その表情だけは年相応に見えた。
「長いこと世界を見てきたが、大人とはつまらん生き物じゃの。近代は特にじゃ」
「そりゃな。じゃ」
いろいろ子供の言葉が気になったけど、変なことに首を突っ込みたくなかったし、俺は関わらないことに決めた。
さっさと帰って一眠りしようと、子供の横を通りすぎた。
「後悔しても知らぬぞ。貴様の部屋を花地獄にしてくれる」
背中に投げかけられた声を無視し、俺はそのまま自宅へ帰った。
どうせ子供の言い分だ。戯言に違いない。
* ※ *
……そして俺は、本当に後悔することになった。
「嘘だろ……?」
帰宅して自分の部屋に向かい、ドアを開いて……すぐさま再び閉めた俺は、足元にまばらに転がるピンク色を見下ろして愕然とした。
『花地獄にしてくれる』
今なら悪魔に見える、あの子供の言葉が蘇った。
さっきドアを開けた瞬間に漂ってきた、肌に触れるだけで汗が噴き出しそうな熱気。それはおかしなことに、嫌でも慣れ親しんだ夏特有のそれだと感覚が告げていた。
いや、それよりも……
一度、深呼吸をし、再び大きく息を吸って。
「おい!おいっ!いるんだろ!」
勢いよくドアを引いた。
途端、堰を切ったように部屋の中からあふれ出てくる無数のピンク色。この季節には絶対有り得ない春の花、桜や梅や牡丹などの大量の花びらだった。
その花の山をかき分けながら踏み込み、ピンク一面の蒸し暑い部屋を見渡す。真夏のような空気に、すぐに額に汗が浮いてきた。
見ると、母さんが気まぐれに置いた、窓辺の植木鉢の花……黄色いハイビスカスが、冬間近なのに満開に開いていた。
その傍らに、この熱気の中、平然とした様子で座る見覚えのある子供。2つのコンペイトウは、やっぱりコイツの周囲を回っている。
「おお、早かったな」
そいつは俺が帰ってきたのを見て、あたかも自分がこの家の者だと言わんばかりの態度で言う。
それがさらに頭に来て、ここが家だということも忘れて、俺は声を荒げていた。
「何だよこれ!! 部屋は暑いし、花で埋もれてるし……お前、一体何なんだよっ!?」
「よくぞ聞いてくれた」
俺はただ腹が立ったから言っただけなのに、そいつは満足そうに笑った。
「わたしは朱夏。夏そのものじゃ」